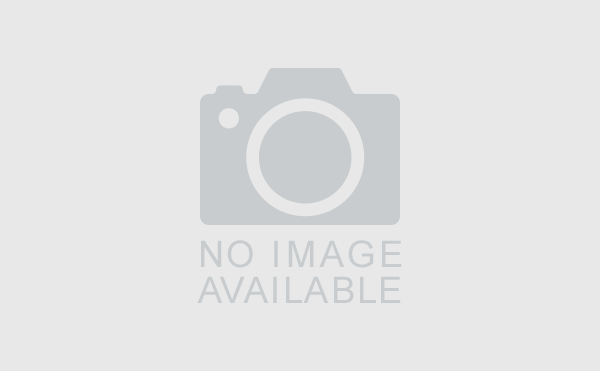エクセルで3年後の日付を出す方法がわからない…そんな悩みをDATE関数で解決!
エクセルで契約日や勤続年数などを管理していると、「3年後の日付を出したい」と感じることがあります。
でも、手入力や足し算で計算すると、うるう年や月末のずれが心配ですよね。
そんなときは、ExcelのDATE関数を使えば、正確に自動計算できます。
クリックできる目次
エクセルで3年後の日付を出すには「=DATE(YEAR(A1)+3,MONTH(A1),DAY(A1))」が便利です
3年後の日付を出す最も簡単な方法は、DATE関数を使うことです。
この関数は、基準のセルを指定するだけで、年・月・日を自動的に計算してくれます。
たとえば、A1に開始日を入力した場合の計算式は次のとおりです。
「=DATE(YEAR(A1)+3,MONTH(A1),DAY(A1))」
この数式の仕組みは次の通りです。
- YEAR関数:A1から年数を取得して3年を加算
- MONTH関数:A1の月を指定
- DAY関数:A1の日付を指定
これで3年後の同じ日付が算出されます。
うるう年や月末の条件にも対応しており、調整は自動的に処理されます。
日数や月数のずれを気にせずに済むので、契約や終了日の管理にも便利です。
Excelの基本機能だけでOKなので、パソコンが苦手な方でも安心して使えます。
Excelのセルに入力して3年後の日付を自動計算する方法
実際の使い方はとても簡単です。
操作は次の手順で行います。
- 基準となる日付をA1セルに入力します。
- B2セルを選択します。
- 「=DATE(YEAR(A1)+3,MONTH(A1),DAY(A1))」と入力します。
- Enterキーを押します。
これでB2セルに3年後の日付が表示されます。
複数のデータに対応したい場合は、B2セルをコピーして下のセルに貼り付けましょう。
すべて自動的に計算されるので、手入力の必要がありません。
もし表示形式が数値(シリアル値)になっている場合は、Excelの「ホーム」タブから「表示形式」をクリックして「日付」を選択してください。
契約の管理や勤続年数の計算など、さまざまな業務データに活用できます。
DATE関数の仕組みと引数をやさしく解説|うるう年も自動で対応
DATE関数は、「DATE(年, 月, 日)」の形で構成されています。
YEAR、MONTH、DAYという3つの引数を組み合わせて、新しい日付を作成します。
この仕組みのおかげで、A1を基準に3年後などの計算を簡単に処理できます。
たとえば、A1が「2022/2/28」の場合でも、2025年がうるう年でなくても問題ありません。
Excelが自動的に調整してくれるため、「2025/2/28」と正しく表示されます。
また、数式内で「+1」や「+6」に変更すれば、月単位やか月単位の計算にも対応可能です。
- 「+1」なら翌年の日付
- 「+6」なら6年後の日付
さらに、B1やA3など別のセルを基準にしても同じ方法で使えます。
書式や形式を変えても正確に算出できるので、データ管理の効率化に役立ちます。
まとめ|3年後の日付をDATE関数で簡単に管理
エクセルで3年後の日付を出すなら、DATE関数を使うのが一番確実です。
A1セルに基準日を入力し、数式を入力するだけで自動的に算出されます。
うるう年や月末の条件にも対応しており、余計な調整は不要です。
契約や終了日、勤続年数などの日付管理にも便利に使えます。
B2セルをコピーすれば、複数のデータにもすぐ対応可能です。
Excelの基本機能を活用して、業務処理をもっとスムーズに進めましょう。
シンプルな関数でも、パソコン作業がぐっと楽になります。