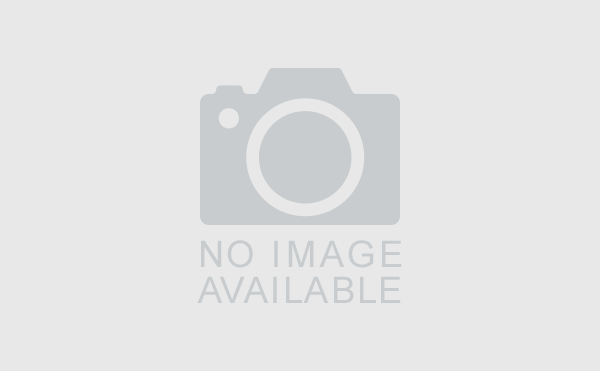【Excel】3つの条件を満たす値を返す方法がわからない方へ|IFS関数でスッキリ解決!
Excelで「3つの条件を満たす値を返したい」と思っても、どの関数を使えばいいのか迷ってしまうことがあります。
IF関数を何重にも入れ子にすると、途中で分からなくなってしまう方も多いです。
そこで今回は、IFS関数を使って、複数の条件を簡単に指定する方法をやさしく解説します。
パソコンに苦手意識がある方でも、この記事を読めばスッキリ理解できますよ。
クリックできる目次
Excelで3つの条件を満たす値を返す方法を解説|IFS関数で簡単に設定できます
まず結論からお伝えします。
3つの条件を満たす値を返すには、IFS関数を使うのが最も簡単で分かりやすい方法です。
IFS関数は、複数の条件を順番に判定して、最初にTRUEになる条件の値を返します。
これにより、入れ子になったIF関数よりもシンプルな数式を作成できます。
=IFS(論理式1, 値1, 論理式2, 値2, 論理式3, 値3)
たとえば、点数が80点以上なら「合格」、60点以上80点未満なら「再テスト」、それ以外は「不合格」と表示したい場合は、次のように入力します。
=IFS(B2>=80,"合格",B2>=60,"再テスト",B2<60,"不合格")
このように、「条件 → 結果」の順に書くだけでOKです。
論理式がTRUEになった時点で処理が止まるため、複雑な分岐を入れ子にする必要がありません。
IFS関数の使い方と引数の指定ポイントを説明します
IFS関数を使うときは、いくつかのポイントを押さえておくと失敗しにくくなります。
IFS関数の引数は次の通りです。
- 論理式:条件を指定します(例:B2>=80)。
- 値:その条件を満たしたときに返す値(例:「合格」)。
設定の手順は以下の通りです。
- 判定したいセル(例:C2)をクリックします。
- 数式バーに「=IFS(」と入力します。
- 最初の条件と値を入力します(例:B2>=80,"合格")。
- 次の条件と値を追加します(例:B2>=60,"再テスト")。
- 最後の条件を入力して「)」で閉じます。
このように、論理式と結果をセットで入力していくだけでOKです。
複数の条件を順番に評価し、最初に一致したものを返す仕組みなので、処理の流れがとてもわかりやすいです。
IFS関数で複数条件の処理をやさしく自動化
IFS関数を使えば、Excelで複数の条件を同時に判定し、最初に一致した結果を自動で返せます。
難しい入れ子や分岐の処理も不要で、初心者でも安心して使える関数です。
最後に、IFS関数を使うときのポイントをまとめます。
- 複数の条件を順番に入力する。
- TRUEを最後に指定してエラーを防ぐ。
- 空白セルも条件に追加できる。
これらを覚えておくと、仕事でのデータ処理や点数評価などにとても便利です。
IFS関数を上手に活用して、Excelでの判定作業をスッキリ効率化しましょう。